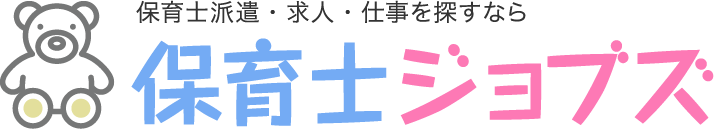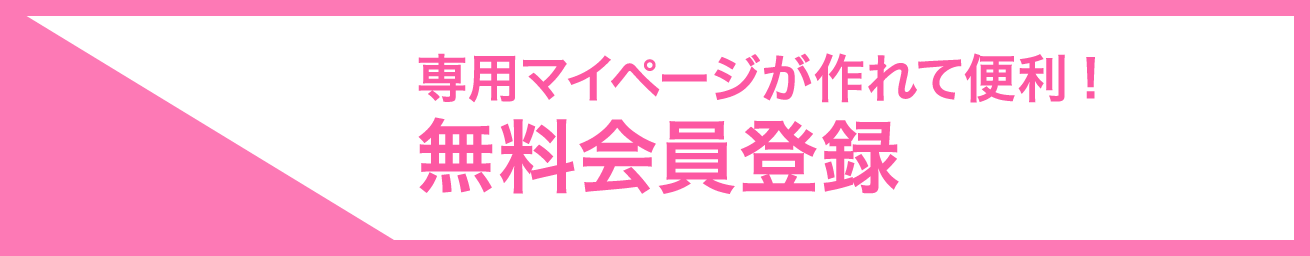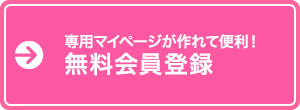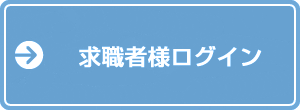お役立ち情報
中堅保育士が専門リーダーを目指す際にありがちな悩み

厚生労働省が「保育士等キャリアアップ研修の実施について」を確立した中で生まれた「専門リーダー」。
主に勤続年数7年以上の中堅保育士を対象としている保育現場のスペシャリストです。
しかし、ベテランと新人の間にはいる立場のため悩みや負担が増えるポジションになります。
専門リーダーを目指す中堅保育士が抱えがちな悩みについてご紹介しましょう。
新人教育が負担
保育施設内において、新人保育士の指導は中堅保育士が任されることになります。
右も左もわからない新人を子どもたちに気を配り、クラスを運営しながら教育することはかんたんなことではないでしょう。
運動会や生活発表会など大きな行事があるときにはかなりの負担に感じるかもしれません。
しかし中堅保育士がストレスで暗い顔をしていると新人保育士はもちろん子どもたちにも影響を与える可能性があります。
ときに先輩保育士のちからを借りながら、笑顔と前向きな気持で新人保育士と向き合うようにしましょう。
中間管理職的ポジションで板挟みに
ベテラン保育士と新人保育士の板挟みになりやすい中堅保育士。
新人保育士とベテランの保育士さんとの橋渡しをしている間に板挟みになることもでてきます。
すばやくできない新人にイライラするベテラン、明確な指示がないため不信感を募らせる新人のどちらの不満も中立に受け止めるとかなりのストレスです。
息苦しさを感じるときには一旦他に相談してみて、それぞれの気持ちを尊重して調整できるように努めたいですね。
退職時強く慰留される
新卒から同じ保育施設で働いていた場合、中堅になる頃には20代後半になるでしょう。
社会人としての経験を重ねていること、年齢的に結婚や出産を考える時期でもあるためこのままの状況で保育士を続けるよりも見聞を広げたいと考える人もいます。
しかし、同じ施設で3年以上働いていることは保育施設側としてなるべく手放したくない存在です。
いざ退職を申し込んだところで強く引き止められるでしょう。そういったことが起きる可能性を認識しておくと一歩踏み出そうとしたときに「ズルズル続けることになった」という事態を避けられます。
周囲の期待がプレッシャーに
「わからないことは○○先生に聞けば大丈夫」と周囲から期待されるシーンが増えてくるのも中堅保育士です。
保育施設側だけでなく保護者からのおぼえもよく、期待されていることがひしひしと伝わることもあるでしょう。
これまでの経験でわかることもあればわからないこともあるので、それがプレッシャーになる方もいます。
相談したくてもできなかったり、自分でなんとか解決しようとしたり。
他の職員に頼らないと解決できないこともあるので、まずは自分ができる範囲で努力し、必要以上に頑張らないようにきをつけましょう