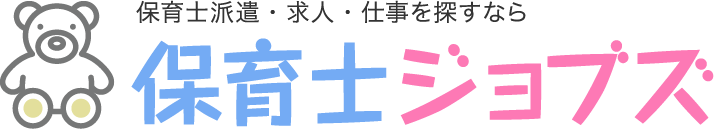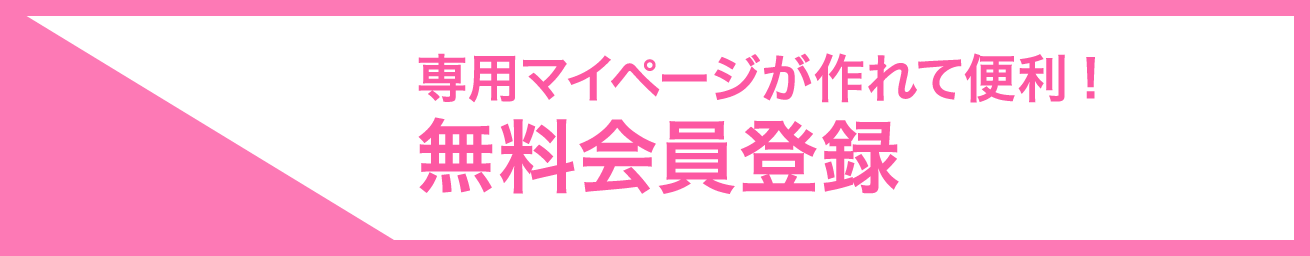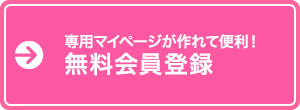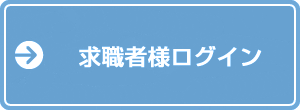お役立ち情報
あのママさん産後うつかも?保育園ができること

保育園に通わせる保護者の中には、産後うつで苦しんでいる方も少なくありません。産後うつは、ホルモンバランスの変化や育児の疲れ、孤独感が原因で引き起こされることが多く、保護者自身が気付いていない場合もあります。
保育士がそのサインに気付き、適切なサポートを行うことは、保護者と子どもにとって大きな助けとなります。
産後うつの兆候とは?
保護者が以下のようなサインを見せている場合、産後うつの可能性があります。
[主な兆候]
表情が暗い、疲れた様子が目立つ
登園・お迎え時に笑顔が少なく、疲労感がにじみ出ている。
コミュニケーションが減少する
保育士や他の保護者と話す機会を避ける、会話が短くなりがち。
ネガティブな発言が増える
「私には育児が向いていない」「子どもがうまく育つか心配」といった自己否定的な言葉。
身体的な不調を訴える
眠れない、食欲がない、頭痛や倦怠感を感じる。
子どもへの関わりが薄くなる
お迎えの際に無表情だったり、子どもへの声かけが少ない。
産後うつの保護者が抱える悩み
産後うつの保護者は、以下のような悩みを抱えていることが多いです。
「育児の孤立感」
「周りに頼れる人がいない」「1人で頑張らなければ」というプレッシャー。
「自己否定感」
「母親失格だ」と感じ、完璧な育児を目指して疲れてしまう。
「他人の目を気にする不安」
他の保護者や保育士から評価されているのではないかという過度な意識。
保育園ができるサポート方法
保護者が「迷惑をかけている」と感じないよう、柔らかい言葉遣いで対応しましょう。
(1)温かいコミュニケーションを心がける
登園・お迎え時のちょっとした声かけが、保護者の心を軽くすることがあります。
無理に深い話を聞こうとせず、相手が安心して話せる雰囲気を作りましょう。
(2)情報提供を行う
産後うつは専門的なサポートが必要な場合も多いです。保育園から、地域の相談窓口や専門機関の情報を伝えることで、適切な支援を受けるきっかけを提供できます。
(3)保護者同士の交流を促す
孤立感を感じやすい保護者にとって、同じ悩みを共有できる仲間の存在は心強いものです。
(4)相談しやすい環境を作る
保育士が「困ったら話してもいいんだ」と思われる存在になることで、保護者が問題を抱え込まずに相談できるようになります。
保育士が注意すべきこと
無理に深く関わらない
保護者が話したくない様子の場合は、そっと距離を置きつつ見守ることも大切です。
専門職の支援を優先する
保育士だけで解決しようとせず、専門機関に相談を促すことが必要です。
子どもへのケアも忘れない
保護者の産後うつが子どもに影響を与える場合もあります。子どもが安心できる環境を整えることが重要です。