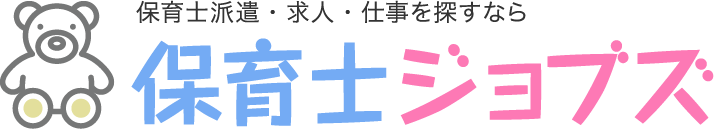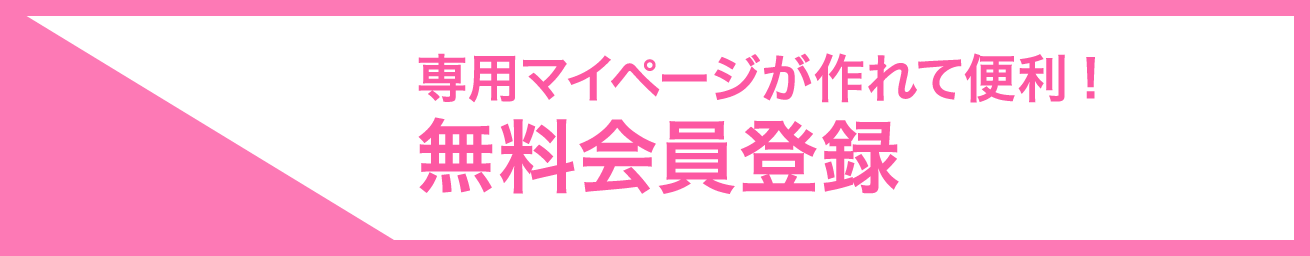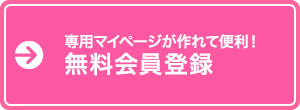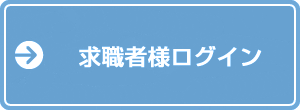お役立ち情報
保育には危険がつきもの②

前回、保育をするうえで危険はつきものであるとご紹介しました。
今回は、どんなことに注意をしていけばよいのかを検証してみましょう。
■身近なヒヤリハットに注意!
このところ、各地で幼い子どもたちが事故に巻き込まれたという悲しいニュースを耳にします。
特に保育者が注意を払っているのが0・1・2歳ではないでしょうか。
この時期、一番多い事故が誤飲等による窒息だといわれています。
この時期は、トライ&エラーともいわれ、それを繰り返すうち、自然と身を守る方法や危ないかどうかの判断をしていく時期にもなります。
かといって、ヒヤリハットの観点で、注意すべきことをピックアップしているので参考にしてみてください。
1.危険なものを避ける
けがや誤飲、窒息の原因になるようなものは、保育室の中には結構存在しています。事前にチェックして、子どもの手の届かないところに置いておくのが基本。周りを見渡して、危険の芽がないか確認しましょう。特に危ないものをピックアップしています。
・ひも
ひもやリボンは子どもが好きなものとしても知られていますよね。
特に、手提げのひもにも注意が必要です。子どもが誤って首に巻きつけてしまわないようしましょう。
・画びょう
誤って手や足で踏んだ場合はもちろん、誤飲は大変危険。壁面を装飾する際は、画びょうの使用は控えましょう。
・コンセント
コンセントは棚などでできるだけ隠しましょう。キャップをしていても子どもが遊んで誤飲に繋がることもありますので、子どもの手が届かない高い位置に設置するのも効果的です。
■保育士は常にゆとりをもって落ち着いた行動を
日々の保育に追われ、忙しくて気持ちに余裕がなくなると、つい危険を見落としてしまうということもあります。そして、不注意からミスや事故につながってしまったなんていうことも。人員の配置が適切かどうか、定期的に見直し、普段から保育士がゆとりをもって行動することが日々の安全に繋がることを忘れてはいけません。
■子ども自身が危険を回避する能力を身につけることも大切
保育士がしっかりと注意をし、子どものけがや事故を未然に防ぐことはとても重要なことですが、子どもから危険を遠ざけているだけでは、子ども自身の危機回避能力を養うことができません。
子ども自身が危険にどう対処し、安全に過ごせる方法を学んでいくことも重要です。
そのためには、子どもの運動能力の発達を促してあげるようにしましょう。会談の上り下りはもちろん、子どもの動きに制限をかけすぎないことが大切です。
また、保護者の理解を仰ぎ、擦り傷や切り傷などの小さなけがの対応方針など、園としての考え方をしっかり説明することも重要です。
保育士の誠意ある対応が、保護者の安心・信頼感に繋がっていくのです。