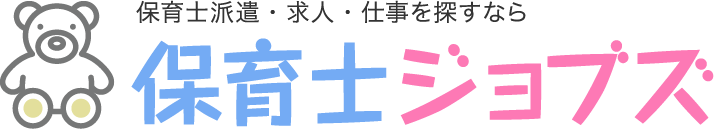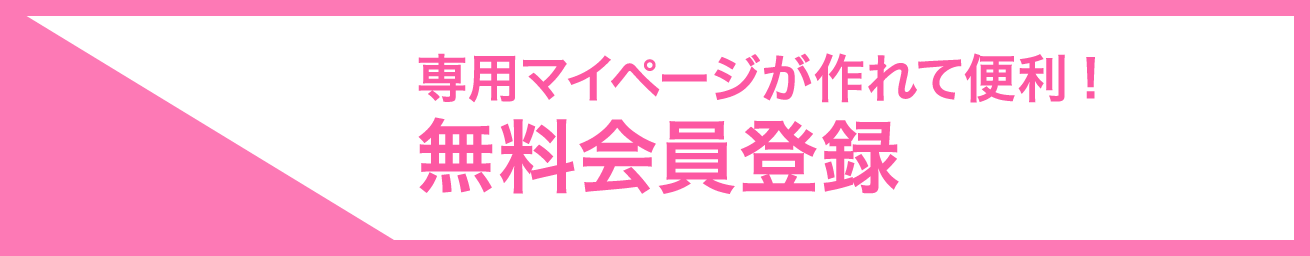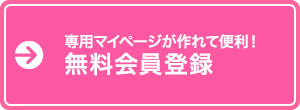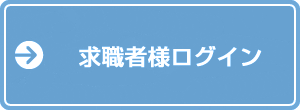お役立ち情報
保護者との連携が大切!離乳食の一般的な流れやアレルギー対応

入園してすぐ離乳食がはじまるというお子さんもいるでしょう。
最初はなかなかうまくいかず、食べる量が少なかったり遊び食べしてしまったり、離乳食のタイミングと母乳やミルクのタイミングが合わなかったりと悩みもでてきます。
保護者の方も同様に悩んでいるので、保育のプロとして成長を見守りつつ支えていきましょう。
こちらでは離乳食の一般的な流れやアレルギー対応についてご紹介します。
離乳食の流れ
準備期(生後6ヶ月ごろまで)
お子さんの成長度合いにもよりますが、だいたい生後5〜6ヶ月くらいから園でも離乳食をはじめます。
ご家庭ではエプロンや深いお皿、スプーンなど離乳食の準備を勧めておくといざ始まる際に慌てずに済むことを伝えておくと良いでしょう。
園では遊びの中で口や下を動かして発達を促します。
初期(生後6ヶ月ごろから)
いわゆる「ごっくん期」です。10倍粥からスタートし、様子をみながら形がのこらない程度に柔らかく茹でて潰した人参やじゃがいも、玉ねぎや白身魚を少しずつ加えていきます。
しっかりと飲み込んでいるか確認しながら「おいしいね」「あーん」と声をかけてコミュニケーションをとり、食事が楽しいものということを伝えていきましょう。
この時期はミルクや母乳で主な栄養は摂ります。便の症状などに注意をしておきましょう。
中期(7、8ヶ月ごろ)
「もぐもぐ期」です。離乳食になれ、喜んで食べるようになれば下と顎で潰して食べられるものを用意します。
お粥も7倍粥に少しずつ移行して、茹でたささみや大根。かぼちゃなどにも挑戦していきましょう。楽しさを味わうのが重要で、ミルクの量は少しずつ減らしていきます。
後期(9、10、11ヶ月ごろ)
「かみかみ期」です。
歯が少しずつ映えてきて、歯でも食べ物をすりつぶせる子もいます。お粥ではなく柔らかいご飯に少しずつ変えていき、手でつかめる人参やさつまいもを柔らかく煮たものを与えてもよいでしょう。
りんごやバナナなどの果物も食べられるようになります。手づかみはムリにやめさせず。まずは自由に食べさせることが大事。
たくさんこぼして汚してしまうでしょうけれど、保護者の方と一緒にのりきりましょう。
口に頬張ってむせて喉につめたりする危険もあるので注意が必要です。
完了期(1歳半ごろ)
「ぱくぱく期」です。食パンなどを噛み切ったり、歯ですりつぶして食べられるものがぐっと増えます。
料理のレパートリーを増やしてお子さんの好奇心を刺激しつつ楽しく食事をしましょう。
スプーンやフォークに興味を示しだしたら少しずつ使えるようにしていく時期です。
保育士が手を添えて食べ方を伝えるとじょじょに子ども自身が使い方を覚えていきます。
子ども自身がうまくつかえずにイライラして癇癪をおこすこともありますが、うまく口に食べ物をはこべたら褒めるようにして、達成感を味あわせましょう。
者や周りの保育者、栄養士としっかり連携をとって進めましょう。
アレルギーへの注意点
離乳食をすすめる上で気をつけたいのがアレルギー。
小児科で行われる主なアレルギー以外のものを発症することもあり、保護者の方もお子さんがもつアレルギーを把握できていないことが多いです。
アレルギーだけでなく、キウイやパインなどで口の周りが荒れる子もいますし、乳製品をうまく消化できない子もいます。
アレルギーは好き嫌いではなく、命に関わる大きな事故になる可能性もあるもの。
万が一の対応ができるよう必要な知識を身に付け、しっかりと情報交換をしておきましょう。
ご家庭でアレルギー反応がでた食材も共有をしてもらい、もし園で湿疹や蕁麻疹、嘔吐、下痢などの症状が現れた場合は、すぐに保護者に連絡して病院を受信しましょう。
小さなお子さんは急速に悪化する可能性もあります。自己判断で保護者と完結してしまわないようにしてください。
離乳食は、成長する上で欠かせない重要なステップ。
食べ物の美味しさ、みんなで食事をする楽しさや自分で食べられる喜びなどを含め、身体が作られるために食事が大切だということを学んでいきます。
大変ですが、アレルギー対応を含め保護者の方としっかりと連携をとって進めていくことが保育士に求められます。