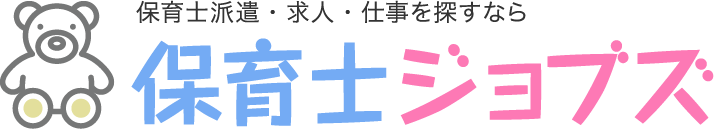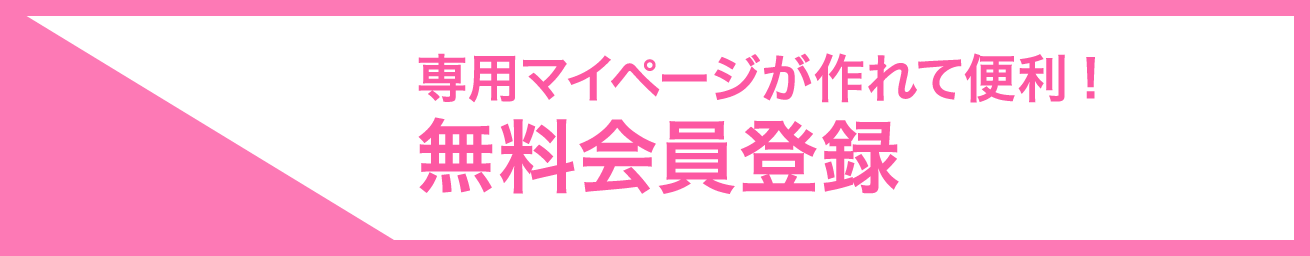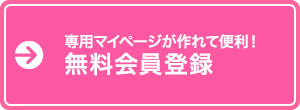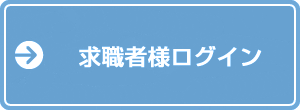お役立ち情報
大学生が防災ハンドブックを考案!「離乳期の子ども」のための災害時の食事は?

9月1日は防災の日。この一週間が防災週間とされています。
保育施設でも各地で防災訓練、避難訓練が実施されますね。
子どもたちの命を守るため、保護者の防災意識を高めるためにも避難訓練などは大切です。
そんな中、保護者向けの防災に関するアンケートが行われ、その結果を受けて大学生が離乳期の子どもがいる家庭に向けたハンドブックを作りました。
防災対策をしていると答えた人は約3割
保護者向けの情報を発信・共有するアプリで行われた防災に関するアンケート。
その中で「備蓄などの災害対策をしている」と答えた人は約3割という結果になりました。
備蓄をされていると答えた方の中で3割弱が「子ども向けの備蓄をしている」と答えています。
・避難所で生活できるか
・子どもの月齢によって揃えるものが変わってくる
・何をどれくらい備蓄すべきかわからない
といったコメントが寄せられました。
必要性の有無と情報の少なさから、子ども向けの備蓄に至っていない保護者の方が多いことがわかります。
離乳期の子どもがいる家庭に向けたハンドブック
ノートルダム清心女子大学の学生らが「離乳中の赤ちゃんがいるご家庭の防災ハンドブック」を作りました。
離乳期は数ヶ月で変化し、子どもが食べるものは限られます。
ハンドブックの対象としているのは、生後5ヶ月から1歳半ぐらいのお子さんがいる家庭で、離乳初期、中期、後期に分けて備蓄するとよいと考えられる1日分の非常食が紹介されています。
防災ハンドブック作成の背景
「防災ハンドブック」はもともと「卒業論文」としてまとめられたものでした。
離乳中の1歳から1歳半ぐらいの赤ちゃんに対する防災指針がないため、卒業研究として取り組まれたことがきっかけです。
離乳期の赤ちゃんに限らず、防災に対する取り組みはまだ具体的に進められていません。
2016年の熊本地震では、ベビーフードなど子ども向けの食材が届いたのは地震発生から10日後。
持ち出しようも含めて少し多めに備えておくことを「防災ハンドブック」では提案しています。
また、栄養バランスを考えてりんごジュースを用意しておくこと、「液体ミルク」を乳児期のお子さんがいる場合は準備したほうがよいことも提案されています。
災害時は精神的なストレスや満足な食事がとれないことから母乳が出なくなること、お湯を沸かす手段がないことが想定されるためです。
ノートルダム清心女子大学の山下准教授は
「そこまで余裕がない家庭がほとんどだろうと思うけれど、できるところからでいいので備えをして、その備え自体よりは備えをしたっていうことで、災害に対する心構え、前向きに取り組むような気持ちを持ってもらえたら、ものすごく考えた甲斐があるなと思います」
と話しています。
「防災ハンドブック」はノートルダム清心女子大学のサイトで閲覧が可能です。
保護者の子育て支援の一環として一読してはいかがでしょうか。