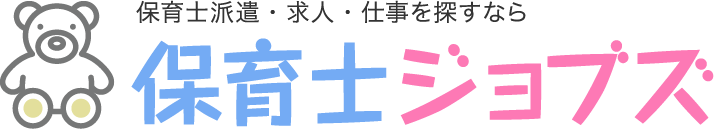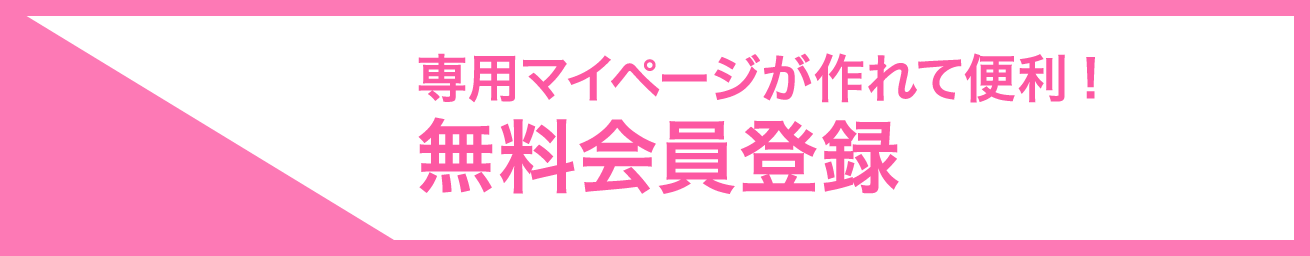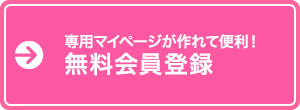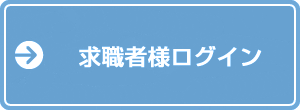お役立ち情報
SIDSと赤ちゃんの生命を守るためにできること

保育の現場でも家庭でも起こりうるSUDI(スーディー)。乳幼児の予期せぬ死です。
その中でも睡眠中の赤ちゃんが突然亡くなってしまうSDIS(乳幼児突然死症候群)。
保育士の午睡チェックが5分おきとなっている要因の一つ。
知識を深めることで絶対とは言わずとも、よりリスクを軽減させることができるのです。
対岸の火事ではない
原因がはっきりしないという定義をもちますが、統計的に発症リスクが高いことがわかって、この15年ほどで激減しました。
しかし年間60名ほどのお子さんが突然死でそのかけがえのない命を落としています。
保育施設での不適切な保育が取り沙汰されている昨今、虐待でもなければニュースでもなかなか取りあげられないSDIS発症は保育士が恐れることです。
大切なお子さんを預かりながら、原因不明で突然失うのですから、保護者にどのように伝えていいのかもわかりません。
しかし、責任は追求されますし、このご時世ですから心無いことを言われることもあるでしょう。
発症率と注意が必要な期間
厚生労働省の統計で冬期、早朝から午前中の間、早産児や低出生体重児、男児の発症が多いことはわかっています。
SIDSの発症率は約6000人〜7000人に1人の割合。
平成9年には538人の赤ちゃんが命を落としているので上記の通り減ってはいるのです。
新生児や乳児が発症しやすいというイメージのSIDS。
実際に生後2ヶ月から6ヶ月の赤ちゃんに多く見られます。
しかし、2歳くらいまでは発症すると言われているので0〜2歳児を担当する場合や、小規模保育施設で従事する場合は注意が注意が必要です。
SIDSのリスクを軽減させるために
うつぶせ寝をさける
厚労省では1歳未満のうつぶせ寝を避けるように言われています。
SIDSで亡くなったお子さんの異常発見時の寝姿は、うつぶせ寝が47.7%、あおむけ寝が39.0%となっています。
うつぶせ寝よりあおむけ寝の方がSIDSの発症確率が低く、異常を発見しやすいと言えるでしょう。
あたためすぎない
大人より体温が高く、熱がこもりがちの赤ちゃん。
睡眠時はあまりあたためすぎないように注意が必要です。
子どもをできるだけひとりにしない
保育士の配置基準を考えると、保育現場では一対一でずっとお子さんを観察しておくことは難しいでしょう。
保育士としてできることは、常に視野を広くもって、子ども全員に気を配れるような意識を持つことです。
喫煙はしない
両親が喫煙する場合と喫煙しない場合では、約4.7倍SIDSの発症率が喫煙する方が高いと言われています。
子どもが好きで保育士になった方で喫煙を続けているという方もすくないでしょうけれど、子どもに関わる仕事に従事する者として、タバコは辞めるのが無難でしょう。
いかがでしょうか。
保育士として業務の一環で取り組んでいることもあれば、自分を律さなければならないこともあるでしょう。
SUDIという新たな概念が生まれ、その中の一つとされたSIDSですが、知識を深めることでそのリスクを軽減することができるということがこの20年間の統計からもわかっています。
子どもたちの命を守るためにできることを身につけていきましょう。